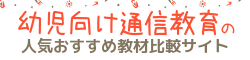タブレットは、幼児の知育や英語学習に便利なツールですが、本当に効果的なのでしょうか?
また、どんな教材やアプリがおすすめなのでしょうか?
この記事では、
タブレット学習のメリットやデメリット、
料金や内容の比較、
市販タブレットや知育アプリの選び方
などを詳しく解説します。
あなたのお子さんに合ったタブレット学習を見つけて、楽しく効果的に学ばせましょう!
タブレットを使った通信教育
スマイルゼミ(年中~)
幼児向けのタブレット教材といえば、唯一あるのが「スマイルゼミ」です。
専用のタブレットを購入して、取り組むスタイルです。
タブレットが反応してくれるので、子供一人で取り組めるのが魅力的。
音声や映像を上手に使って、タブレットならではの学びが得られます。

小学生向け講座の先取り(チャレンジタッチ)
タブレット教材でスマイルゼミと同じくらい有名なものが「チャレンジタッチ」です。
ただし、コース設定が小学生以上のものしかありません。
もしも受講するなら先取り学習になってしまいます。
年長向けの教材をなんなくこなせるなら、先取りでタブレット教材を取り入れるのも良いでしょう。
市販タブレットで使える学習アプリ
ひらがなが学べるおすすめ知育アプリ
学研の幼児ワーク ひらがな・カタカナ~もじ判定つき~(無料)
学研の作っているアプリです。
学研のクオリティで無料でできるアプリです。
文字に興味を持ち始めた頃におすすめです。![]()
しまじろうの知育アプリ
![]() こちらは有料になりますがしまじろうのアプリです。
こちらは有料になりますがしまじろうのアプリです。
ひらがな以外のことも学べる総合知育アプリです。
あいうさがし – がんばれ!ルルロロ(無料)
![]() Eテレでもおなじみの可愛らしいキャラクタールルロロ。
Eテレでもおなじみの可愛らしいキャラクタールルロロ。
簡単な操作で、ひらがな&見つけ遊びが楽しめます。
機内モード(オフライン)でも使えるアプリ
アプリを使っていて気になるのが、オフラインの状態でも使えるかどうかです。
無料アプリの場合は、途中で出てくる広告収入で運営しているものがほとんどです。
そのため、機内モード(オフライン)にすると動かなくなってしまうものもあります。
すべてのアプリを試したわけではありませんが、
有料アプリのほうが、機内モードでも安定して使える確率が高いです。(広告が出ない)
子どもに使わせるお勉強タブレットおすすめ
Androidのタブレット
![]() 中身は普通のAndroidタブレットですが、
中身は普通のAndroidタブレットですが、
- 5,000円前後の価格
- タブレットカバー付き(キッズ用)
- 知育アプリインストール済み(課金なし)
という条件を考えると、コスパのバランスの良いタブレットです。

iPad
 |
|
Apple iPad (Wi-Fi, 32GB) – スペースグレイ 新品価格 |
![]() iPadはドコモやソフトバンクなどの通信会社で買うもの、Amazonなどで買えるものがあります。
iPadはドコモやソフトバンクなどの通信会社で買うもの、Amazonなどで買えるものがあります。
違いは通信の部分で、携帯電話会社で買うと、もれなく通信プランをセットで契約します。
Amazonなどの通販で買う場合は、SIMフリータイプと言って通信用のSIMカードが別売りになっています。
自宅のWIFI環境だけで使うならSIMフリー版だけで十分です。
SIMフリー版(Amazonなどで買えるもの)は相場が5万円前後。
携帯電話会社のものなら、本体だけなら実質0円でも買えます。
WIFI以外でも使う予定があるなら、携帯会社で契約するのも良いかもしれません。
今使っているスマホとのセット割や、自宅の光回線との割引を使えばお値打ちに手に入ります。
Amazon タブレットキッズモデル
 |
|
Fire 7 キッズモデル ピンク (7インチディスプレイ) 16GB 新品価格 |
![]() アマゾンから新しく出た、子ども用のタブレットです。
アマゾンから新しく出た、子ども用のタブレットです。
Amazonが提供する子ども用の知育アプリが2年間使い放題になる特典付きです。
ベースは普通のファイアタブレットなので、やや割高に感じます。
ただ、キッズモデルということで手厚い保証がついてます。
2年間は、落下や水濡れなどの故障にも対応してくれるのは嬉しいです。
こどもが使うものですからね。
おもちゃのタブレット
![]() 本物のタブレットよりも、おもちゃの延長のほうがいい場合は、
本物のタブレットよりも、おもちゃの延長のほうがいい場合は、
小学館のNEOPadのようなタブレット玩具もあります。
完全に決められた機能しか使えないおもちゃです。
動きは普通のタブレットに似ているので子どもは喜びます。
タブレット学習は目が悪くなるか心配
タブレット学習をさせていると気になるのが、ブルーライト&視力の低下です。
テレビはある程度距離を持って見ることができますが、タブレットとなると顔を近づけて見てしまいます。
姿勢も悪くなりそうですよね。
実際に、私もパソコンを触るようになってから視力が落ちました。
子供の頃はよくテレビゲームをしてましたが視力はとても良かったのです。
テレビ画面と、PCやスマホ・タブレットはやはり違います。
タブレットを触れる時間を制限する機能を上手に使って、
あまり長時間触りすぎないようにしてあげたほうがいいですね。