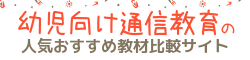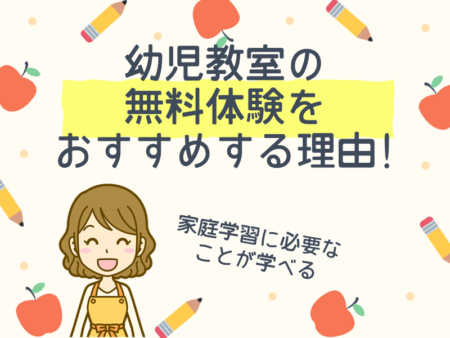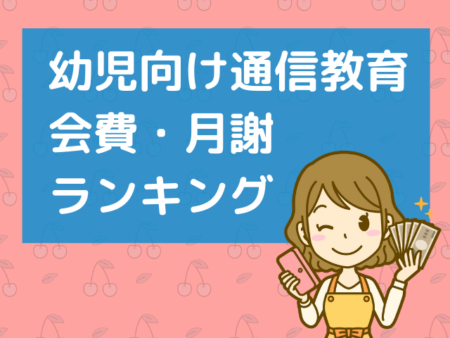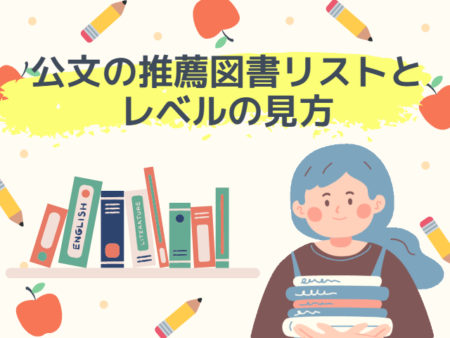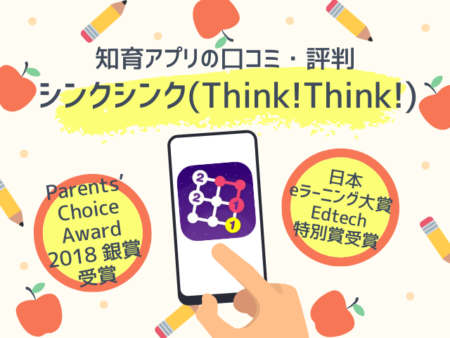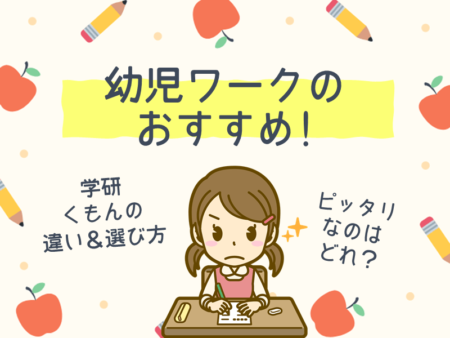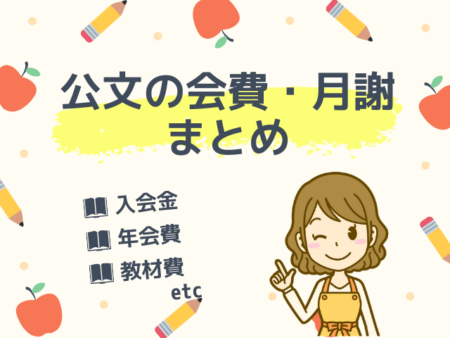先取り学習に興味があるけど、どんな教材がいいのかわからない…そんな悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
先取り学習とは、自分の学年よりも上の内容に挑戦することで、学力や知識を伸ばす方法です。
しかし、先取り学習には注意点やデメリットもあります。
例えば、一学年上のコースに進むと、小学校入学時に困ってしまったり、先取りしすぎて学校の授業がつまらなくなったりする可能性があります。
そこでおすすめなのが、「無学年式」の通信教育です。
無学年式とは、自分のレベルに合わせて国語や算数などの分野ごとに先取り学習ができるサービスです。
無学年式なら、自分の得意な分野だけ先取りしたり、年齢に応じたコースと併用したりすることができます。
この記事では、無学年式で先取り学習に向いている通信教育を3つご紹介します。
それぞれの教材の特徴や料金、無料お試し情報などもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
教材ごとのレベルの違いをチェック
そもそも、同じ年少・年中・年長向けのものでも、通信教育の種類によって難易度は異なります。
もしかしたら、先取りをせずに別の教材に変えるだけでも、納得のいく内容に出会えるかもしれません。
参考までに教材別の難易度はこちらにまとめてあります。

先取り学習にむいている幼児の通信教育
こどもちゃれんじ じゃんぷタッチ(タブレットコース)
こどもちゃれんじのタブレット専門コース「じゃんぷタッチ」です。毎月、タブレットにワークが配信され取り組む通信教育です。
年長(じゃんぷ)コースの8月号からは、「AI国語算数トレーニング」という無学年学習サービスが利用できます。
年長さんからでも、小学1年生~中学生までの分野を、レベルに合わせて先取り学習ができます。
学年を飛ばして受講する場合に比べて、年令に応じたコースの教材を受け取りつつ、得意な分野(計算や漢字など)を、それぞれ先取りできます。漢字だけ6年生レベル、計算は3年生、メイン教材は年長さんで入学準備のワークに取り組めるという組み合わせでも利用可能なところが魅力的です。
スマイルゼミ

スマイルゼミは年中から受講できるタブレット教材です。メインの教材とは別に、「コアトレ」という無学年学習のサービスがあります。
学齢にあった毎月の教材とは別に、国語と算数を先取り受講できます。幼児コースから最大中学生のコースまで先取り可能です。
どちらの通信教育も、タブレットを使って学習を進めるので、子どもの興味をひきやすく、楽しく学習を進めることができます。また、無学年制なので、自分の学習レベルに合わせて先取り学習をすることができます。
先取り学習を検討している方は、ぜひこれらの通信教育を検討してみてください。
天神
![]() 第10回日本e-Learning大賞にてグランプリとなる大賞を受賞!
第10回日本e-Learning大賞にてグランプリとなる大賞を受賞!
モンテッソーリ教育の考えを採用した知育教材で、0歳から6歳までの子どもにぴったり!
- タブレットでなぞって書く練習に対応
- 日本語と英語のフラッシュカード2000枚以上
- 5系統59ジャンル、約10000問を反復学習
- 兄弟姉妹が3名まで無料で利用可能
先取り学習の注意点・デメリット
年長児に小学コースをとるかどうか
一学年先取りをすると、困ってしまうのが年長進級児です。
そのまま、小学コースに進むか、一旦お休みするか迷いますね。
難しさを感じずに取り組むことができるかもしれませんが、キャラクターの舞台が「小学校」になったりすると戸惑うかもしれません。
また、小学コースになると受講システムが変わる教材も多いのも悩みのひとつになります。
また実際に通う小学校の教科書指定なども必要になります。
最近は無学年学習を取り入れた教材も増えてきたので、年齢通りの教材に追加で先取りをする使い方がおすすめです。
先取りしすぎて学校の授業がつまらなくなる
幼児のうちは、決まった学習要領がないので先取りをしても特に何も感じません。
ところが、小学校にあがると決まった教科書の通り学習を進めることになります。
先取りしすぎていると、わかりきった内容を説明される退屈な時間を過ごすことになります。
以前、テレビでインターナショナルスクールのインタビューを見ましたが、そこは先取りに熱心でした。
ところが、その授業はすべて英語でおこなわれていて日本語での補習はしていませんでした。
なぜなら
「小学校に上がってから授業で退屈しないように、日本語での学びは残しておいてあげてます」
という考え方なのです。
英語で理解している、「化学・地学・歴史・数学」などの知識を、小学校からは日本語で学び直してね。というスタイルなのです。
これなら先取りしていても、小学校の授業で退屈しませんね(たぶん(^_^;))
というように。
あまりに先取りしすぎると、小学校生活が苦痛になってしまいますよ。というお話でした。
子どもにぴったりのレベルの教材を探すには?
とはいえ、簡単過ぎる教材に取り組むことが良いとも思いません。
当たり前ですが、幼児でも簡単過ぎる課題には飽いてしまいます。
ちょっと頑張らないと解けないくらいの問題に取り組むと、解けたときに快感を覚えて「勉強好き」な子に育ちます。
これは今受講中の、ポピーの考え方です。
今、子どもが夢中になれて、ちょっと難しいかな(?)くらいの教材を用意してあげることが大切です。
- 子どもの学習状況や性格に合わせて、先取り学習の量や内容を調整する
- 子どもが先取り学習に飽きないように、さまざまな学習方法を取り入れる
- 子どもが先取り学習でつまずいたときには、適切な指導を行う
レベルの見極めにはお試し教材を使うと便利です。
違う学年のものも同時に取り寄せると、先取り学習に向いているかどうかが判断しやすいです。
ぜひ取り寄せて試してみてください。